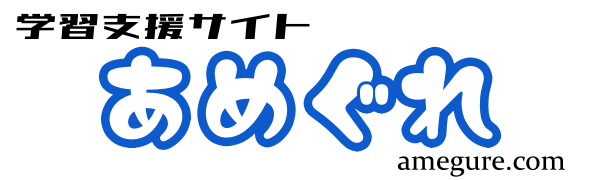ダートマス会議(だーとますかいぎ/Dartmouth Conference)
概要
ダートマス会議は、1956年にアメリカのダートマス大学で開催された人工知能(AI)研究の発足点とされる会議です。ジョン・マッカーシーらによって企画され、数週間にわたって開催されました。この会議で「人工知能」という言葉が初めて公式に使用され、AI分野の出発点として歴史的に重要視されています。
一言で表すと
AI研究の始まりを告げた会議
関連する用語
・人工知能(AI)
・ジョン・マッカーシー
・シンボリックAI
・機械学習
・チューリングテスト
ルールベース(Rule-based)
概要
ルールベースとは、あらかじめ人間が定めたルール(if-then形式の条件分岐など)に従ってシステムが動作する方式です。専門知識を持つ人が明示的に記述したルール群によって判断や推論を行います。人工知能の初期に用いられたアプローチであり、専門家システムなどで使われました。
一言で表すと
人が作ったルールで動く仕組み
関連する用語
・エキスパートシステム
・機械学習
・知識ベース
・if-thenルール
・推論エンジン
機械学習(きかいがくしゅう/Machine Learning)
概要
機械学習は、コンピュータが明示的なプログラムなしにデータからパターンを学習し、予測や分類などのタスクを行う技術です。統計的手法を用いてデータからモデルを構築し、新しいデータに対しても一般化された判断を下すことが可能になります。現在のAI技術の中核をなす分野です。
一言で表すと
データから学ぶコンピュータの技術
関連する用語
・教師あり学習
・教師なし学習
・深層学習(ディープラーニング)
・特徴量
・汎化能力
学習済みモデル(がくしゅうずみもでる/Trained Model)
概要
学習済みモデルとは、機械学習において訓練データを用いて学習を完了した後のモデルを指します。パラメータが最適化されており、新しいデータに対して推論や予測を行える状態です。多くの場合、学習には大量のデータと計算資源が必要ですが、学習済みモデルを使えば再学習せずにすぐに利用できます。
一言で表すと
使えるようになったAIモデル
関連する用語
・機械学習
・推論
・パラメータ
・モデルの再学習
・転移学習
特徴量(とくちょうりょう/Feature)
概要
特徴量とは、機械学習モデルに入力するデータの中で、予測や分類に役立つとされる属性や数値のことです。元のデータから意味のある情報を抽出・変換して得られ、モデルの性能に大きな影響を与えます。効果的な特徴量の設計は、モデルの精度を高める鍵となります。
一言で表すと
予測に役立つデータの要素
関連する用語
・前処理
・特徴量エンジニアリング
・次元削減
・教師あり学習
・データ正規化
ディープラーニング(Deep Learning)
概要
ディープラーニングは、多層のニューラルネットワークを用いてデータから特徴を自動的に学習する手法です。画像認識、音声認識、自然言語処理など多くの分野で高い性能を発揮しています。大量のデータと高性能な計算資源により、従来の機械学習を超える成果を上げています。
一言で表すと
多層構造で学ぶAIの中核技術
関連する用語
・ニューラルネットワーク
・活性化関数
・誤差逆伝播法
・畳み込みニューラルネットワーク(CNN)
・深層強化学習
非構造化(ひこうぞうか/Unstructured)
概要
非構造化とは、データの形式が一定でなく、明確な構造(行や列)に従っていない状態を指します。画像、音声、動画、自然言語テキストなどが代表例で、機械による自動処理が難しいとされてきました。ディープラーニングなどの技術により、非構造化データの活用が進んでいます。
一言で表すと
形式が決まっていないデータ
関連する用語
・構造化データ
・自然言語処理
・画像認識
・ビッグデータ
・ディープラーニング
AI効果(えーあいこうか/AI Effect)
概要
AI効果とは、ある技術が「AIによる成果」として注目されていたのに、その技術が一般的になり理解されると「もはやAIではない」と見なされる現象を指します。AIの定義が進化する中で、過去に革新的とされた技術が日常的なものとされ、AIの境界が曖昧になることがあります。
一言で表すと
理解されるとAIと思われなくなる現象
関連する用語
・人工知能
・汎用人工知能(AGI)
・専門家システム
・機械学習
・ディープラーニング
第1次AIブーム(だいいちじえーあいぶーむ/First AI Boom)
概要
第1次AIブームは1950年代後半から1960年代にかけて起こり、推論や探索を中心とした「記号処理型AI」に期待が集まりました。当時はパズル解決や迷路探索などで一定の成果がありましたが、現実世界の複雑さへの対応が困難で、期待ほど成果が出ずに停滞しました。
一言で表すと
記号処理への過剰な期待と限界
関連する用語
・記号処理
・探索
・ルールベース
・エルIZA
・AIの冬
第2次AIブーム(だいにじえーあいぶーむ/Second AI Boom)
概要
第2次AIブームは1980年代に起こり、エキスパートシステム(専門家の知識をルールとして記述するシステム)が注目されました。推論エンジンと知識ベースによって専門的判断を模倣する試みが進みましたが、ルールの増加による管理の困難さや柔軟性の欠如が問題となり、再び停滞しました。
一言で表すと
ルール依存の知識型AIの全盛期
関連する用語
・エキスパートシステム
・ルールベース
・知識ベース
・推論エンジン
・AIの冬
エキスパートシステム(えきすぱーとしすてむ/Expert System)
概要
エキスパートシステムは、特定分野の専門家の知識をルールとしてコンピュータに組み込み、判断や推論を行う人工知能の一種です。1980年代の第2次AIブームを牽引し、医療診断や設備保守などに応用されましたが、知識の更新やルール管理の難しさから限界が指摘されました。
一言で表すと
専門家の知識をルール化したAI
関連する用語
・ルールベース
・知識ベース
・推論エンジン
・第2次AIブーム
・AIの冬
第3次AIブーム(だいさんじえーあいぶーむ/Third AI Boom)
概要
第3次AIブームは2010年代以降に起こり、ビッグデータと高性能な計算資源を背景に、機械学習と特にディープラーニングの成功により広がりました。画像認識、音声認識、自然言語処理など多くの実用的成果が現れ、産業や社会に大きな影響を与えています。
一言で表すと
データと計算力で開花したAI革命
関連する用語
・機械学習
・ディープラーニング
・ビッグデータ
・GPU
・汎化能力
実世界の複雑な問題(じつせかいのふくざつなもんだい/Complex Real-World Problems)
概要
実世界の複雑な問題とは、現実社会において発生する予測困難で多様な要因が絡み合う課題のことです。ノイズや不完全な情報、人間の常識や文脈の理解が求められるため、初期のAI(記号処理型AI)では対応が難しく、AIの進化を阻む要因となってきました。現在のAIは機械学習やディープラーニングによって、これらの問題への対応力を高めています。
一言で表すと
AIにとって扱いづらい現実の課題
関連する用語
・記号処理
・機械学習
・常識推論
・ノイズ
・汎用人工知能(AGI)
知識獲得のボトルネック(ちしきかくとくのぼとるねっく/Knowledge Acquisition Bottleneck)
概要
知識獲得のボトルネックとは、エキスパートシステムなどにおいて専門家の知識を明示的なルールとしてシステムに取り込む作業が非常に困難かつ非効率であるという課題を指します。知識を抽出・整理・形式化するには専門家とエンジニアの協力が不可欠で、これがAIの発展を妨げる要因の一つとされてきました。
一言で表すと
専門知識をAIに教える難しさ
関連する用語
・エキスパートシステム
・知識ベース
・ルールベース
・第2次AIブーム
・機械学習
DENDRAL(デンドラル)
概要
DENDRALは1960年代にスタンフォード大学で開発された、化学分析(特に有機化合物の構造推定)を支援するエキスパートシステムの先駆けです。専門家の知識をルールとして組み込み、質量分析データから分子構造を推論しました。初期の成功例として、エキスパートシステムの有用性を示しました。
一言で表すと
化学推論に特化した初期AIシステム
関連する用語
・エキスパートシステム
・ルールベース
・知識ベース
・MYCIN
・第2次AIブーム
MYCIN(マイシン)
概要
MYCINは1970年代にスタンフォード大学で開発された医療用エキスパートシステムで、細菌感染症の診断と治療支援を目的としていました。専門医の知識をルール化し、症状や検査結果から適切な抗生物質を提案します。性能は医師に匹敵すると評価されましたが、法的・倫理的課題から実用化はされませんでした。
一言で表すと
感染症診断に特化した医療AI
関連する用語
・エキスパートシステム
・ルールベース
・知識ベース
・DENDRAL
・第2次AIブーム
CASNET(キャスネット/Causal Associational Network)
概要
CASNETは1970年代に開発された医療用エキスパートシステムで、特に眼科(緑内障など)の診断支援に用いられました。因果関係に基づいたネットワーク(Causal Associational Network)を用いて、症状・病理・治療の関連性をモデル化し、推論を行います。エキスパートシステムの中でも、因果推論を重視した代表例です。
一言で表すと
因果関係で診断する医療AI
関連する用語
・エキスパートシステム
・因果推論
・知識ベース
・MYCIN
・第2次AIブーム
探索、推論(たんさく、すいろん/Search and Inference)
概要
探索とは、問題空間の中から解や最適な経路を見つけ出す手法であり、AIにおける問題解決の基本です。一方、推論は既知の知識から新たな知識や結論を導き出す過程を指します。第1次AIブームでは、この2つを組み合わせた記号処理型AIが中心であり、ルールに基づいた処理が主流でした。
一言で表すと
知識を使って解を探す仕組み
関連する用語
・記号処理
・ルールベース
・エキスパートシステム
・問題空間
・状態遷移
探索木(たんさくぎ/Search Tree)
概要
探索木とは、問題解決の過程を木構造で表現したもので、各ノードが状態を、枝が状態遷移を示します。AIでは、最初の状態から目標状態へ到達する経路を見つけるために、探索木を使って様々な可能性を体系的に調べます。ゲームAIや経路探索、論理推論などで広く利用されます。
一言で表すと
解への道を木構造で探す方法
関連する用語
・探索
・状態空間
・幅優先探索
・深さ優先探索
・評価関数
幅優先探索(はばゆうせんたんさく/Breadth-First Search)
概要
幅優先探索は、探索木やグラフの探索手法の一つで、開始ノードから近い順にすべてのノードを調べていく方法です。まず隣接ノードをすべて探索し、その次に次の階層に進むという手順を繰り返します。最短経路が保証される利点がありますが、メモリ消費が大きくなる傾向があります。
一言で表すと
近くから順に調べる探索法
関連する用語
・探索木
・深さ優先探索
・状態空間
・キュー
・最短経路
深さ優先探索(ふかさゆうせんたんさく/Depth-First Search)
概要
深さ優先探索は、探索木やグラフにおいて、ある経路をできるだけ深く進んでから分岐点に戻る探索手法です。一つの枝を深くたどり、行き止まりに達したら戻って別の道を探すという形で進行します。メモリ使用量は少ない一方で、最短経路が得られるとは限らない点に注意が必要です。
一言で表すと
奥へ進んでから戻る探索法
関連する用語
・探索木
・幅優先探索
・状態空間
・スタック
・バックトラック
イライザ(ELIZA)
概要
イライザは、1960年代にMITのジョセフ・ワイゼンバウムによって開発された初期の対話型プログラムで、ユーザーの入力に対して決まったパターンで返答する擬似的な会話を実現しました。精神分析医を模したスクリプト「DOCTOR」が有名で、人間のように会話していると錯覚させる効果が話題となりました。
一言で表すと
初期の会話型AIプログラム
関連する用語
・自然言語処理
・ルールベース
・Turingテスト
・チャットボット
・第1次AIブーム
Cycプロジェクト(サイクぷろじぇくと/Cyc Project)
概要
Cycプロジェクトは、1984年にアメリカのダグラス・レナットが開始した人工知能研究プロジェクトで、常識的知識を体系的に記述し、大規模な知識ベースを構築することを目的としています。論理ベースで知識を表現し、推論エンジンによって人間のような理解を目指すアプローチですが、膨大な知識の手動入力に膨大な労力が必要という課題もあります。
一言で表すと
AIに常識を教える超大型計画
関連する用語
・知識ベース
・推論エンジン
・ルールベース
・記号処理
・知識獲得のボトルネック
意味ネットワーク(いみねっとわーく/Semantic Network)
概要
意味ネットワークは、知識をノード(概念)とリンク(関係)で表現する構造で、概念同士の意味的な関係を可視化します。「犬は動物の一種」「犬は鳴く」などのように、オブジェクトや属性、階層関係などをネットワーク上に表現することで、推論や検索が可能になります。記号処理型AIの知識表現手法の一つです。
一言で表すと
概念同士の関係をつなぐ知識構造
関連する用語
・知識表現
・オントロジー
・記号処理
・推論
・フレーム
オントロジー(Ontology)
概要
オントロジーは、特定の分野における概念や用語、そしてそれらの関係を明確に定義・体系化した知識の構造です。意味ネットワークやフレームの発展系であり、AIやセマンティックウェブなどで共有・再利用可能な知識モデルとして活用されます。概念の分類や階層構造、属性、関係性などを形式的に記述することが特徴です。
一言で表すと
知識を整理した意味の設計図
関連する用語
・意味ネットワーク
・知識表現
・セマンティックウェブ
・フレーム
・記号処理
ヘビーウェイトオントロジー(Heavyweight Ontology)
概要
ヘビーウェイトオントロジーは、概念の階層構造や関係性だけでなく、厳密な制約条件や論理的推論も可能とする高度に定義されたオントロジーです。定義の厳密さにより、形式的推論や知識の一貫性チェックが可能で、AIやセマンティックウェブにおける知識共有や再利用の信頼性を高めます。
一言で表すと
推論まで可能な精密知識構造
関連する用語
・オントロジー
・意味ネットワーク
・知識表現
・セマンティックウェブ
・記号処理
ライトウェイトオントロジー(Lightweight Ontology)
概要
ライトウェイトオントロジーは、基本的な概念の階層構造や用語の定義に重点を置いた、比較的単純で軽量なオントロジーです。厳密な制約や論理的推論までは含まず、主に情報の共有・分類・検索などを目的としています。導入や構築が容易なため、実用的なシステムで広く利用されます。
一言で表すと
簡易で実用的な知識分類構造
関連する用語
・オントロジー
・意味ネットワーク
・分類体系
・知識表現
・セマンティックウェブ
ワトソン(IBM Watson)
概要
IBM Watsonは、IBMが開発した高度な人工知能(AI)システムで、自然言語処理や機械学習を活用して人間のように情報を理解し、意思決定を支援します。2011年に米国のクイズ番組「Jeopardy!」で人間のチャンピオンに勝利し、その名を世界に知らしめました。以降、医療、金融、教育など多岐にわたる分野で活用され、AIの実用化を牽引しています。
一言で表すと
人間の意思決定を支援するAIシステム
関連する用語
・自然言語処理(NLP)
・機械学習
・コグニティブ・コンピューティング
・IBM watsonx
・Deep Blue
セマンティックウェブ(Semantic Web)
概要
セマンティックウェブは、ウェブ上の情報に「意味(セマンティクス)」を持たせ、人間だけでなくコンピュータも情報の意味を理解・処理できるようにする構想です。情報にメタデータを加えることで、より高度な検索や推論が可能になります。W3Cが提唱し、RDFやOWLなどの技術が用いられます。
一言で表すと
意味を理解する次世代のウェブ
関連する用語
・RDF(Resource Description Framework)
・OWL(Web Ontology Language)
・トリプル
・LOD(Linked Open Data)
・オントロジー
LOD(Linked Open Data / リンクト・オープン・データ)
概要
LODとは、公開されているデータをURIで識別し、他のデータとリンクさせることで、ウェブ上で意味的につながったデータ空間を構築する取り組みです。セマンティックウェブの実現に向けた実践例として位置付けられ、政府データや図書館データなどで活用が進んでいます。
一言で表すと
意味でつながる公開データの集合
関連する用語
・セマンティックウェブ
・RDF
・オントロジー
・SPARQL
・URI(Uniform Resource Identifier)
弱いAI(よわいえーあい / Weak AI)
概要
弱いAIは、特定のタスクに特化した人工知能で、汎用的な知能や自意識は持ちません。音声認識、画像分類、検索エンジンなど、多くの現代のAIシステムが該当します。あくまで道具として人間を支援する目的で設計されています。
一言で表すと
特定タスクに特化したAI
関連する用語
・強いAI
・機械学習
・ディープラーニング
・専門特化型AI
・人工知能
強いAI(つよいえーあい / Strong AI)
概要
強いAIは、人間のような汎用的な知能を持ち、自ら思考し、理解し、学習できる人工知能を指します。現在はまだ実現されておらず、哲学的・倫理的な議論の対象にもなっています。人工汎用知能(AGI:Artificial General Intelligence)と同義として扱われることもあります。
一言で表すと
人間並みの汎用知能を持つAI
関連する用語
・弱いAI
・人工汎用知能(AGI)
・意識
・チューリングテスト
・シンギュラリティ
トイ・プロブレム(Toy Problem)
概要
トイ・プロブレムとは、AIやアルゴリズムの研究・開発において用いられる、簡略化された問題設定のことです。現実の問題をモデル化して理解・解決しやすくするために使用され、チェスや迷路探索、8パズルなどが例として挙げられます。現実の複雑な問題を解く前段階として、理論検証やアルゴリズムの性能評価に役立ちます。
一言で表すと
研究用の簡単な模擬問題
関連する用語
・探索アルゴリズム
・状態空間
・8パズル
・迷路問題
・ゲーム木探索
チューリングテスト(Turing Test)
概要
チューリングテストは、AI(人工知能)が人間と区別がつかないほど自然に会話できるかどうかを判定するためのテストで、アラン・チューリングが1950年に提案しました。人間の審査員が対話相手が人間かAIかを識別できなければ、AIは「知的」とみなされます。AIの知能を評価する初期の指標とされました。
一言で表すと
AIが人間らしく会話できるかの試験
関連する用語
・アラン・チューリング
・強いAI
・自然言語処理
・知能の定義
・イミテーション・ゲーム
シンボル・グラウンディング問題(しんぼる・ぐらうんでぃんぐもんだい / Symbol Grounding Problem)
概要
シンボル・グラウンディング問題は、「記号(シンボル)」が意味を持つには、それが何か実世界の対象や経験に結びついていなければならない、という問題です。AIが辞書的な定義だけで語を理解している場合、実際には「意味を理解していない」とされることから、真の意味理解の課題として注目されます。
一言で表すと
記号が意味を持つための根本問題
関連する用語
・知識表現
・意味理解
・強いAI
・セマンティックウェブ
・知能の哲学
フレーム問題(ふれーむもんだい / Frame Problem)
概要
フレーム問題は、AIが状況の変化に対応して、何が変わり、何が変わらないかを適切に判断するのが難しいという課題です。行動の結果を推論する際に、無関係な情報を省略して重要な変化だけを扱うのが困難で、知識の表現や効率的な推論が求められます。
一言で表すと
状況変化への判断が難しい問題
関連する用語
・知識表現
・論理推論
・計画問題
・認知アーキテクチャ
・常識推論
爆弾とロボット(ばくだんとろぼっと / The Bomb and the Robot)
概要
「爆弾とロボット」はフレーム問題を説明するための有名な思考実験です。爆弾が置かれた部屋にある箱をロボットが取り出そうとするとき、その行動が他の危険(例:爆弾の起動)を引き起こさないかを事前に判断するのが困難であることを示します。AIがすべての影響を正確に推論することの難しさを表しています。
一言で表すと
フレーム問題を示す例題
関連する用語
・フレーム問題
・常識推論
・知識表現
・ロボティクス
・AI倫理
シンギュラリティ(Singularity)
概要
シンギュラリティ(技術的特異点)は、AIの能力が人間を超え、自己進化によって急速に知能が発展する未来の時点を指します。レイ・カーツワイルらが提唱し、2045年頃に到達すると予測されていますが、正確な時期や実現可能性には議論があります。社会や倫理に与える影響も大きな関心事です。
一言で表すと
AIが人間知能を超える転換点
関連する用語
・強いAI
・人工汎用知能(AGI)
・加速する技術進化
・AI倫理
・レイ・カーツワイル